
実は、電池は身近な道具でつくることができるんだ。キャンプなどで使う炭の一種・備長炭を使って電池を作ってみよう!

おすすめの年齢・制作時間
工程などが少しだけ複雑なので、理科の授業で回路などについて一通り習った4年生以上がおすすめ。
4年生 5年生 6年生 実験 製作期間:1日
用意するもの

備長炭
アルミホイル
キッチンペーパー
食塩
水
輪ゴム
ハサミ
コップ
豆電球とソケットなど
電池ができているか確かめるために、豆電球やソケット、電子メロディなども用意しよう。
手順
1.キッチンペーパーを塩水にひたす

コップ半分の水に食塩を入れてよくかき混ぜる。その中にキッチンペーパーをひたす。
<ポイント>
- コップの水の底に食塩が残るくらい、濃[こ]い食塩水をつくろう。食塩は水を温めても溶[と]け方はあまり変わらないので、常温でOK。キッチンペーパーはしぼりすぎないで、ひたひたくらいに食塩水が残っているようにしよう。
2.備長炭にキッチンペーパーをまく

キッチンペーパーを軽くしぼって、備長炭の端[はし]が2cmくらい出るように包み込[こ]む。
3.アルミホイルでくるむ

キッチンペーパーが1cm出るくらいアルミホイルを巻く。その上からアルミホイルがずれないよう輪ゴムを巻く。
4.豆電球とつなぐ

備長炭が出ている部分とアルミホイルの部分にそれぞれアルミホイルを上から巻き、豆電球のソケットの電線をつなぐ。
5.豆電球を光らせてみる
電線をつなぐと、豆電球が点灯する。うまくつかないときはアルミホイルの部分をしっかり握[にぎ]る。豆電球だと暗いので、電流が少なくてもいいLEDや電子メロディなどで試すのもおすすめ。
<ポイント>
- 豆電球ではなく電子メロディなどをつなぐときは、備長炭の部分にプラス、アルミホイルの部分にマイナスのコードをつなごう。
まとめ方のコツ
・豆電球にもいろいろな種類があり、消費電力の値(A)が低いほど光りやすいよ。豆電球の光り方の違いを比べてまとめてみよう。
・備長炭をいくつかつくって、直列回路と並列回路を試してみよう。強い電気が発生するのはどちらかな?予想を立てて実験しよう。
<どうして備長炭で電池がつくれるの?>
- アルミホイルでを塩水につけると、アルミホイルが溶[と]けて電子が発生するんだ。備長炭の中には多くの酸素があって、この酸素がマイナスの電子を受け取ろうとする。そうすると、アルミホイルから備長炭に向かって電子が移動し、電池が流れているんだよ。
参考にした本
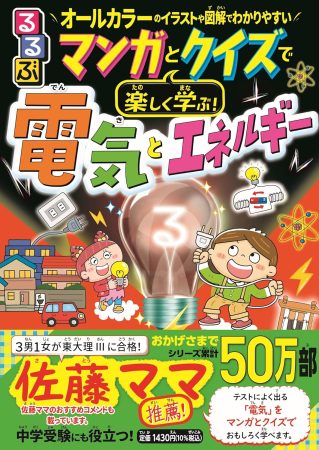
『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!電気とエネルギー』
つまずきやすい理科の単元「電気」を、イラストやマンガでやさしく解説!「電流」や「回路」などをはじめ、おうちでできるカンタン実験、これからの未来を支える電気とエネルギーの最新技術の紹介など、身近な電気のひみつを学ぼう。













