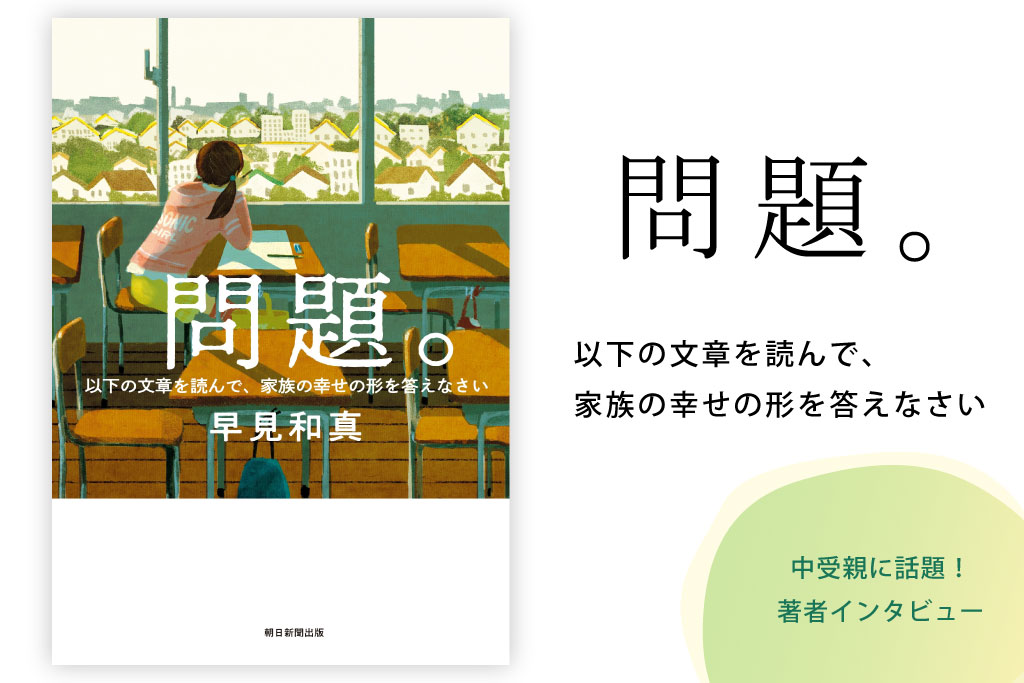
僕は中学受験を「超肯定的」にとらえている――。作家・早見和真さんの新刊『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』(朝日新聞出版、1760円)は、中学受験を軸に、主人公・十和(とわ)ら少女たちの思春期の心の揺れと家族のあり方を、あざやかな筆致で描いた小説です。中学受験の持つ意味や向き合い方について、早見さんに話を聞きました。(撮影:朝日新聞出版写真映像部)
 作家・早見和真さん
作家・早見和真さん
1977年神奈川県生まれ。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。2015年『イノセント・デイズ』で日本推理作家協会賞、2020年『ザ・ロイヤルファミリー』でJRA賞馬事文化賞、山本周五郎賞を受賞。同年『店長がバカすぎて』が本屋大賞第9位に入賞。2025年『アルプス席の母』が本屋大賞第2位に入賞。主な著書に『6 シックス』『95』『笑うマトリョーシカ』『八月の母』、シリーズに『かなしきデブ猫ちゃん』などがある。

「中学受験の結果はどうでもいい」理由

年々、熱を帯びる中学受験。模試の実施や入試情報の提供を行う首都圏模試センターによると、2025年春の首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)の私立・国立中学校の受験者総数(推計)は5万2000人ほどでした。早見さんの長女も数年前に中学受験を経験し、第一志望の学校に合格しました。
しかし早見さんは「大前提としてうそ偽りなく、僕は彼女が落ちても受かってもいいと思っていた」と語ります。「僕は志望校に受かった結果、幸せになる確率は50%だと思っている。一方で落ちた結果、あのとき悔しかったという思いに支えられて幸せになる確率も50%だと思っている」
早見さんがそう考えるのには理由がありました。「僕も中学受験の経験者で、当時第一志望として人気のあった学校に通ったものの、今その卒業生を見れば、自分も含めてそんなに大したものにはなっていない。だから、中学受験の結果はどうでもいいと体験談で持っている」
そのうえで「12歳という一瞬、自分がまだ定まっていない中で、何か釈然としないまま、ただがんばるという行為は圧倒的に肯定できる」と早見さんは語ります。作中、登場人物たちが語る「(主人公が将来)自伝を書くとする。そこで綴られる中学受験のことなんて、一行か、二行くらいのもの」、「中学受験なんかしなきゃ良かったって声は(中略)聞いたことがない」といった言葉は、早見さんの強い思いだそうです。
一方で「中学受験の結果にのめり込んでいる保護者を、僕は受け入れられない」といいます。「中学受験の結果にだけコミットしている保護者から見れば、この物語はきれいごとに見えるかもしれない。ところが読後の感想として、子どもが中学受験に挑む保護者から、意外にも『気持ちが軽くなった』という声を多く頂いた。近視眼的にのめりこんでいる人たちに、俯瞰する視点を提供できたのではないか」と出版の手ごたえを語ります。
家族に腹くくらせる中学受験
本作について「そもそも中学受験を書きたかったわけではない」と早見さん。
「以前から父と娘の物語を描きたかった。世の中によくある『父に虐待された娘の話』や『寡黙だった父の死後に明かされる温かな話』といった類型的でない物語にしたかった」そうです。しかし「早見家について言えば、父と娘の間に『お互いに嫌われたくない』という薄い膜のようなものが間にあって仲が良く、お互いがむき出しになることがなかった」ため「ここに物語は生まれない」と考えていました。
そこに現れたのが「中学受験というあまりに理不尽な、彼女の手に余る化け物じみた敵」でした。
早見さん一家は当時、愛媛県松山市に住んでいました。2月に試験が行われる都内の学校を第一志望としていた長女は、1月初旬に県内の私立中学の受験が終わった瞬間から、それまで塾で切磋琢磨していた友人らが受験を離れ、たった一人になってしまいました。中学受験にあえて触れないようにしていた早見さんですが「直接SOSを出されたことはない」ものの「やけに話しかけてくる」など長女の変化を感じ、そこから第一志望の学校の試験までの1カ月、「娘と肩を組んで中学受験という敵と向き合うことになった」。「あの1カ月が、これまでで一番笑い合い、上っ面ではない本音の話を一番した」と振り返ります。そして「この1カ月を煮詰めれば父と娘の物語が生まれるという確信があった」
「僕の持論として、どんないびつな家族でも、いざ何かあったときに一丸となって立ち向かえるのが本物の家族というのがある。毎晩食卓を囲む家族がいい家族とは思っていない。いざというときに腹をくくれるのが家族。早見家にとって中学受験がそれだった」
社会の矛盾を突きつける

中学受験の特徴として、早見さんは「12歳」という年齢に注目します。
「思春期の一番面倒なときにぶつかるのが中学受験」と早見さん。「娘の周囲を見ていると、男子は保護者に気持ちよく乗せられて疑問を抱くことなく挑んでいるように見えた。一方で女子は男子のいわゆる『中2』が小6にあたる感じで、さまざまな理不尽を消化できないまま挑まざるをえない」
物語は主人公の十和とその家族を中心に描かれますが、同じく中学受験に挑む女子の友人たちの姿もそれぞれ印象的です。誰もが自分ではどうすることもできないものと向き合いながら、必死に合格を、そしてその先にあるものをつかみ取ろうとします。しなやかで温かな筆で描かれる少女たちの生き生きとした姿が、読み手の心を揺さぶります。
とはいえ早見さんは、中学受験をしないという選択肢を否定するわけではありません。「中学受験で合格して幸せになる可能性が50%だとするなら、公立に行って幸せになる可能性だって50%」と話します。
ただし「公立にしか行けないというのであれば、それは正しくない。あの学校でこれを学びたい、この部活をがんばりたいという子の希望がかなわないというのはどうにかすべきだ。僕の持論は『当たり前にがんばっている人が当たり前に幸せになるのが正しい社会』だ。その意味では、がんばりたいという子にがんばれる環境を提供できないこと、がんばっている人が幸せになれないことは、僕たちの世代が今の社会を生み出したのだとすれば、それはぼくらの敗北だ」。作中、ある登場人物が引き起こす「事件」は、保護者世代に社会の矛盾を鋭く突きつけます。
著者でも難しい!中学受験の小説問題
早見さんといえば、2025年の本屋大賞2位になった『アルプス席の母』(小学館、1870円)をはじめ、これまで多くの小説が中学受験で使われてきました。著者として「使ってくれた学校のことが断然好きになる(笑い)。ただ同じ小説を使っていても学校によって難易度が違っていて興味深い」といいます。
「中学受験に向けて、僕の小説を読むというのは一つの手かもしれない。特に今回の『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』は中学受験が物語の軸なので問題を作りやすいのでは……と言いたいところだけど、書いた僕自身が解けないこともあるので絶対とはいえません(笑い)」
最後に、早見さんは読者へのメッセージとして「子どもはもちろんだけど、まず保護者に読んでほしい」と話します。「親としてコミットすべきは中学受験の結果ではなく、子どものがんばり。子ども時代の子どもと関われる最後の機会が中学受験。そこに悔いを残さないでほしい」
中受を終えた「るるぶKids」編集長のコメント
「次の文章を読み、家族の幸せの形を、文章中の言葉を使って40字以内で答えない」という文章題を前にした小6の主人公・十和が、「そんなのあるならこっちの方が知りたいって」とつぶやく模試の場面から物語がはじまります。
そらそうだ。大人でも難しい難題を、小6が簡単に解けるわけないよねぇ…と、わが子の受験期によく思っていたことを思い出します。そこから一気に物語の世界へ引き込まれ、主人公家族と共に一喜一憂して読み進めました。
12歳という思春期の入口に経験する中学受験を通して、家族が懸命に向き合い成長していく過程は、少なからず多くの受験親にも重なるところがあるのではないでしょうか。
ネタバレになるので詳細は控えますが、主人公と家族、友達、周囲の人々との会話には、受験合格だけではない大切なことを気づかせてくれるフレーズが多く登場します。わが家の背中も押してもらえたような読後感。今子育てに向き合う方々に、ぜひ読んでみてほしい一冊です。子どもが小学校高学年なら、親子で感想を伝え合うのもおすすめです。来年の受験にも出るかもしれませんね!
書誌情報
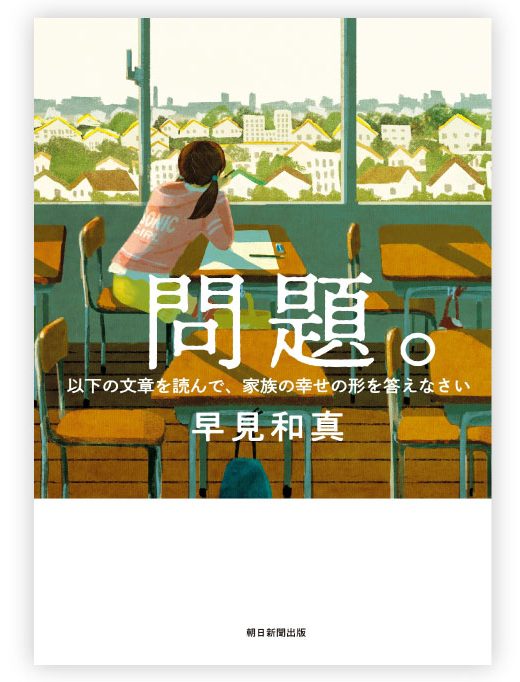
| 書名 | 問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい。 |
|---|---|
| 著者 | 早見 和真 |
| 判型 | 四六判並製 360ページ |
| 定価 | 1760円(税込) |
| 発売日 | 2025年3月7日 |
| 発行 | 朝日新聞出版 |
▼中学受験の体験談を聞かせてください!
るるぶKidsでは、中学受験の体験談を募集しています。抽選で100名様にAmazonギフト券をプレゼントいたします。ぜひ、みなさまの貴重な体験談をお聞かせください。
»中学受験の体験談アンケート
▼中学受験の関連記事
» 読書が苦手でなくなる!朝10分の習慣は?
» 中学校選びの選択肢は?公立・国立・私立の特徴や入試方法を解説
» 中学受験に向いてる子は?偏差値だけじゃない3つの特徴
» 子どもの個性を伸ばす志望校の選び方
» 子育て世代のNISA術 教育費はいくらかかる?
»佐藤ママ×脳科学者パパ対談 中学受験のメリット 幼児期の過ごし方や習い事は?













