
子どもの中学受験を視野に入れたママパパ必見!子どもの性格ややりたいことに合った学校の選び方を、インスタグラムで人気の中学受験インフルエンサー「がくパパ」が詳しく解説します。昨今の中学受験トレンドでは、偏差値だけが学校選びの基準ではありません。子どもの個性を伸ばす学校選びを全力でサポートします!
▼中学受験の体験談を聞かせてください!
るるぶKidsでは、中学受験の体験談を募集しています。抽選で100名様にAmazonギフト券をプレゼントいたします。ぜひ、みなさまの貴重な体験談をお聞かせください。
»中学受験の体験談アンケート
▼中学受験の関連記事
» 中受に作品がよく出題される作家・早見和真さんの最新刊インタビュー
» 読書が苦手でなくなる!朝10分の習慣は?
» 中学校選びの選択肢は?公立・国立・私立の特徴や入試方法を解説
» 中学受験に向いてる子は?偏差値だけじゃない3つの特徴
» 子育て世代のNISA術 教育費はいくらかかる?
»佐藤ママ×脳科学者パパ対談 中学受験のメリット 幼児期の過ごし方や習い事は?
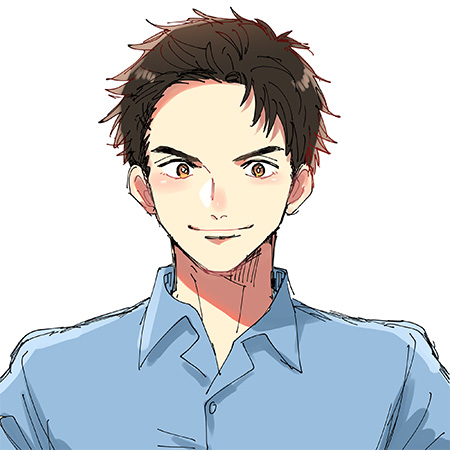 著者:がくパパ
著者:がくパパ
「偏差値だけで学校を選ばない」をモットーに首都圏の中学受験校100校以上を独自に調査し中学受験校を分かりやすく解説しているインスタグラムを運営中。学校が好きすぎて、私立校の講師も経験した学校ヲタク。今は3児(5歳・2歳・0歳)のパパ。
≫ がくパパInstagram

中学受験、いつから考えるべき?

画像:PIXTA
中学受験を意識し始める時期としては、小学校4年生頃から塾(小3の終わり・2月入塾が一般的)や通信教育などに通い始める家庭が多いです。ただ、実際のところは子どもの学習習慣や興味関心によって大きく異なります。
フォロワーさんの中には「今は幼稚園児ですが、もう中学受験を考えています」という方や、「小学校受験とどちらにするか悩み中」というご家庭も。とはいえ、塾に行く時期や習い事をやめるタイミングなどは各家庭の事情に合わせて検討する必要があります。
「学ぶこと」を楽しめる子は受験に向いている!

画像:PIXTA
受験への早めの準備を意識するがあまり、テストの点数を上げることだけに注力しすぎると、子ども自身がもっている探究心やワクワク感を損ない、学ぶ意欲を失ってしまう恐れがあります。
幼少期から小学校低学年ぐらいまでの時期は、まずは、「学ぶこと」「知ること」を純粋に楽しめる気持ちや好奇心を育てておくことこそが大切です。
実際に中学受験を経験したフォロワーさんにアンケートをとってみると、「知的探究心のある子」「勉強が好きな子」「得意科目がある子」など、学ぶこと自体を楽しめる子ほど中学受験に向いているとの声が多くありました。
まずは日常生活での習慣づくりから始めよう

画像:PIXTA
自分の興味関心を伸ばせる学校を選ぶ——これこそが中学受験の大きなメリットでもあります。まずは家庭学習や読書、日常の中で「なぜ?」「どうして?」と問いかけ、調べる機会を増やすなど、遊び感覚で知識を深める習慣を作ってみましょう。こうした土台があると、4~5年生頃に本格的な受験対策を始めても、「学ぶ楽しさ」を失わずに受験勉強にもスムーズに取り組みやすくなります。
子どもに合う学校を選ぶポイント

画像:PIXTA
中学受験は「どの学校に入るか」がゴールのように思われがちですが、本当に大切なのは、その後の6年間をどのような環境で過ごし、どんな力を身につけるかということです。数多くの学校見学や保護者の方々と交流してみて、学校の特色によって子どもの成長が大きく変わると強く感じています。
ここでは、学校選びのポイントを3つ挙げ、それぞれのメリットや特徴を簡単にご紹介します。ぜひ、お子さんの性格や興味関心に合いそうかどうかをイメージしながら考えてみてください。
①男女別学or共学
●男女別学(男子校・女子校)
同性同士ならではの一体感や結束力が生まれやすいのが大きな魅力です。男子校ではエネルギッシュなスポーツや文化祭を楽しみやすかったり、女子校では周囲の目を気にせず自分を伸ばせるなど、それぞれの良さがあります。特に「異性の目を気にしなくていい」点は、思い切り自分の興味や特技に打ち込める環境づくりにつながります。
●共学
日常的に異性とのコミュニケーションがあるため、自然と協調性や社会性が育つのが特徴です。行事や部活動などでも多様な交流があり、人間関係の幅が広がる傾向があります。男子校・女子校とはまた違った活気やチームワークの盛り上がりを感じやすいのもポイントです。
②進学校or附属校
●進学校
難関大学への進学率が高く、受験対策カリキュラムが充実していることが多いです。大学受験を本格的に目指す子にとっては刺激的な環境で、ハイレベルな仲間と切磋琢磨できます。
●附属校
内部進学制度が整っているため、大学受験のプレッシャーが比較的少ないのがメリット。部活動や留学、探究学習など、幅広い経験に時間を使いやすい学校も多いです。ただし、学校によっては内部進学条件が厳しい場合も…。近年は「他大学受験」を積極的にサポートする附属校も増えているため、大学の事業報告書などをチェックしておくと、学校の方針を深く知ることができます。
③伝統校or新設校
●伝統校
長い歴史とOB・OGネットワークが強みです。行事や部活動にも確かな蓄積があり、学校全体に一体感や格式を感じられます。卒業生とのつながりが強く、将来の進路や就職活動でもサポートを受けやすいメリットがあります。
●新設校
生徒の自主性を重視するプログラムや、少人数対話型授業などを取り入れているケースが多いです。特に「英語」「サイエンス」「探究」などに力を入れる学校が増えており、実社会でも活かせるスキルを伸ばしやすい環境が整っています。
伝統校にはない新しいチャレンジを楽しめる校風が強みで、在校生も積極的に行事や学習プログラムを“創り上げる”意識が高い印象があります。
いま挙げた例はほんの一部で、学校それぞれに異なる強みや特色があります。 「ここなら子どもがイキイキと過ごせそう!」と感じるかどうかは、実際に足を運んでみるのがいちばん。パンフレットやホームページだけでは分からない“リアルな雰囲気”を、ぜひ説明会やオープンキャンパスで体感してみてください。
子どもに合う志望校選び、6つのチェックポイント

画像:PIXTA
中学受験で「どの学校を志望校にするか」を決める際は、親子でしっかり意思をそろえることが大切です。親は合格実績や偏差値が気になるかもしれませんが、子どもは校風や部活動を重視することもしばしば。志望校選びがうまくいく家庭ほど、親子で情報を共有しながら話し合いを重ねているという印象があります。
独自の教育内容は?
グローバル教育やSTEAM教育などを柱にする学校が増えています。英語ディベートやプログラミング、大学との高大連携プログラムなど、学校ごとの特徴もさまざま。お子さんが興味を持つテーマ(ロボット・AI・デザインなど)がある場合、それに関連した授業やクラブ活動が充実しているかを確認してみましょう。文化祭や授業公開の様子を見て、より具体的な学びの内容を把握するのがおすすめです。
大学の合格実績は?
難関大学への合格率や附属校での内部進学実績は、将来を見据えるうえで大切な要素です。たとえば「指定校推薦の枠がどれくらいあるか?」や「内部進学の条件がどの程度厳しいか?」などをチェックしてみてください。ただし、数字だけにとらわれず、子ども自身がどのような進路を希望しているかを踏まえて考えることが重要。理系志望の女子が多い学校や、実は文系に強い学校など、イメージと実態が異なるケースもあるので、複数の情報源を比べてみるとよいでしょう。
学校生活は?
中学・高校の6年間を過ごす場所なので、普段の生活や行事、部活動、設備面、制服なども要チェック。文化祭や体育祭、修学旅行の行き先などがその学校ならではの特色を示している場合も多いです。僕が見学したなかには、海外研修や自然体験に力を入れている学校、IT教育環境を整備している学校など、実に多様な事例がありました。子どもが「毎日通うのが楽しみ!」と思えるかどうかは、実際に生徒の様子や施設の雰囲気を見るのがいちばんわかりやすいです。
学校の施設状況
ここ数年、改修工事やDXハイスクール事業などで新しい設備を導入している学校も増えています。パンフレットやホームページを見ると「とてもかっこいい最先端の教室」の写真に目を奪われがちですが、実際に行ってみると、その施設だけ最新で、他はあまり整備が進んでいない……というケースも。必ず学校を訪問し、全体的な環境を見て判断することをおすすめします。
先生たちをよく見てみる
説明会や文化祭で先生方の様子をしっかり観察するのもポイントです。広報担当の先生だけでなく、ほかの先生方がどのように動いているかも見てみましょう。駅から学校までの案内をしている先生、舞台裏で準備を手伝っている先生などの様子から、学校全体のチームワークや雰囲気が感じられるはずです。
通学手段・時間は?
見落とされがちなのが、通学手段や通学時間。片道1時間以上かかる場合、塾との両立や体力面で負担が大きくなることがあります。学校によっては寮があったり、スクールバスを運行していたりと、サポート体制が異なるため、無理なく通える距離と手段を考慮しておくのが大切です。
親子で同じ視点に立つのは難しいこともありますが、情報を共有してお互いに意見を伝え合うことが後悔しない学校選びのコツ。パンフレットや説明会だけではわからない“リアルな雰囲気”を、文化祭やオープンキャンパスで感じ取り、親子でしっかり話し合いましょう。そうした体験を重ねるうちに、「子どもがワクワクできる学校」と「親が安心して送り出せる学校」の両立が見えてくるはずです。
中学受験で絶対やるべき2つとは!

画像:PIXTA
親子で一緒に考え、チャレンジする
中学受験は、子どもにとっても保護者にとっても大きなチャレンジですが、保護者がしっかり伴走できる最後の受験ともいわれます。高校や大学の受験では、子ども自身が塾や予備校を選び、スケジュール管理をする場面が増えるため、親が深くかかわれる機会は案外限られてくるからです。
だからこそ、「どの学校が子どもの個性を最も伸ばせるか」を親子でじっくり考え、納得のいく選択をしたいもの。塾や周囲から得られる偏差値や合格実績の情報は貴重ですが、数字だけに振り回されると本来の学校の良さを見落としてしまうこともあります。僕は多くの学校を実際に見学し、授業や部活動、校内の雰囲気に触れたからこそ、「パンフレットだけではわからない魅力」を数多く感じました。
偏差値で絞るまえに!学校見学へ出かけよう
学校見学や文化祭、オープンキャンパス、オンライン説明会などを活用し、在校生や卒業生の口コミも含めて幅広く情報を集めてみてください。そうすると、学校の実像が立体的に見えてきます。多くのご家庭から「中学受験は大変だったけれど、やってよかった」という声を聞いてきました。塾の成績表や偏差値ランキングだけでなく、子どもの性格や興味、将来の夢などを総合的に考えながら、「この子がイキイキと学べる環境」を探してみてください。親子で同じ目標に向かって話し合いながら進むプロセスは、かけがえのない経験になるはずです。
中学受験はゴールではなく、その後の6年間を充実させるためのスタートライン。広い視野と柔軟な発想をもって、親子で納得のいく学校選びができるよう応援しています!













