
ねり消しゴムをいろいろなかたちに変えて、どうすると水に浮[う]くのか調べてみよう。おうちにあるもので気軽に取り組めるよ!

おすすめの年齢・制作時間
かたちだけでなく素材を変えて試すこともできる、シンプルながら奥[おく]の深い実験。「なぜ」をつきつめるなら4年生以上がおすすめ。
3年生 4年生 5年生 6年生 実験 製作期間:3日
用意するもの

ねり消しゴム
大きめのものだと、いろいろなかたちを作れるよ。ねんどを使っても実験できるよ。
コップ
透明[とうめい]なコップがおすすめ。横から観察できるよ。
水
ペットボトルのふた1個
手順
1.丸めたねり消しゴムで実験

丸めたねり消しゴムを、水の入ったコップに入れるとどうなるか見てみる。
2.おわんのかたちにする

水から取り出したねり消しゴムに、ペットボトルのふたを押[お]しつけて外し、おわんのようなかたちに整える。
3.水に浮[う]かべる
おわんのかたちをしたねり消しゴムを水に浮かべる。他に魚のかたち、へびのように細長いかたち、平らなかたちなどで試してみる。
<豆知識:どうして水の上で浮くかたちがあるの?>
- 地球上の物体は、重力によって地球の中心方向に引っ張られる。つまり下向きの力がかかっている。重力があるのに物体が水に浮くのは、水から重力と同じだけ上向きの力を受けるから。この、水から受ける力を「浮力[ふりょく]」というよ。
- 水を入れたコップの水面に、1円玉を縦に置くと沈[しず]むけど水平に静かに置くと浮く。これは浮力のほかに、水の表面の面積を最小にする「表面張力」という性質がはたらいているからなんだ。
まとめ方のコツ
・浮くかたちと沈むかたちをグループ分けして、気付いたことをまとめてみよう。
・浮いた(沈んだ)かたちと同じかたちの物体を探して、同じように水の中に入れてみよう。その物体は浮いたかな?沈んだかな?ねり消しゴムと違[ちが]う結果が出た場合は、どうして違う結果になったのか考えてみよう。
・浮いている様子や沈んでいる様子を写真に撮[と]っておくとわかりやすいね。
参考にした本
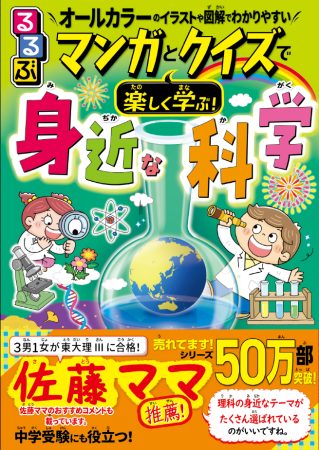
『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!身近な科学』
『炭酸水はどうやってできるの?』『どうして明かりに昆虫[こんちゅう]が集まってくるの?』など、私たちの生活の中にあるふしぎと科学のつながりを、豊富な図や資料、イラストでわかりやすく紹介。身近な道具でできる実験コーナーにも注目!













