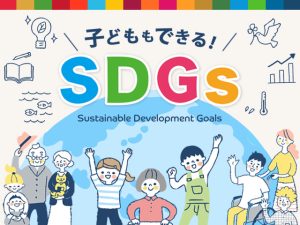2020年のはじめから続く新型コロナウイルス禍ですが、いまもまだ終息の目途がたちません。その間、家族または子どもたちの日常生活も、これまでとは大きく変わることになりました。「るるぶKids」では、このwithコロナの1年間について、そしてこれからのニューノーマル時代の子育てについて、識者や「子ども」に関わる職業に従事する方にインタビュー。第3弾は、養育者と子どもの関係性と子どもの社会情緒的発達などについて専門に研究されている、東京大学大学院教育学研究科教授の遠藤利彦先生に、コロナ禍でも非認知能力が問題なく育つのか伺いました。
 遠藤利彦先生
遠藤利彦先生
1962年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得後退学。博士(心理学)。東京大学大学院教育学研究科教授。発達保育実践政策学センター(Cedep)センター長。
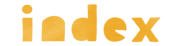
幼児期の体験が人生を豊かに。「非認知能力」が育つ条件
近年、幼児教育において「非認知能力」が大きなテーマとなってきていることは、ご存知の方も多いと思います。2017年度に改定が告示された、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にある「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」、通称「10の姿」の中にある「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」などは、この非認知能力に関連する項目とされています。
非認知能力は人生を通して毎日を豊かなものにするために大切なもの。これを育むにあたって大切なのは、就学前の環境だといいます。ただ、コロナ禍のような状況下では、通常と同じ環境を用意できない……もしかしたら非認知能力がうまく育たないかもしれない。そう心配される人も多いかもしれません。
まずは、この非認知能力とは何かについて、改めて遠藤先生に伺いました。

遠藤:非認知能力とは、「自己に関わる心の力」と「社会性に関わる心の力」を合わせたものと言えます。前者は自分のことを大切にし、適度にコントロールし、自分をもっと良くして高めようとする力のこと。一般的に私たちが日常的に使うことばで言えば、“自”という漢字が入る言葉(自尊心、自己肯定感、自信、自制心、自立心、自己理解など)のことです。一方、後者は集団生活にうまく溶け込んで、人間関係を維持する力と考えると良いと思います。
人と上手くやっていくためには、相手の気持ちを理解する能力や、共感や思いやりというのも大切な要素。また、集団生活のためには協調性も、何がよくて何が悪いかをちゃんと判断する能力、さらに言えばルールや決まりを守る力も必要になってきます。このような心の力を持っていれば、私たちはそこそこ上手いこと人との関係を作っていけるし、自分の可能性を自分自身で実現していける。健康で幸せに生きていくために、誰もが直感的に必要だと思うものが非認知能力と言えるのではないでしょうか。
信頼できる大人と「アタッチメント」関係を築くことの重要性

では、この大切な幼児期に、非認知能力を高めるためにやらなければならないこととは何なのでしょうか。
遠藤:基本的に非認知能力というのは、特別な働きかけの中で身につくというよりは、日常的な大人との相互作用や子ども同士の関わり、自発的な遊びの中で育まれるものだと考えています。
例えば幼稚園や保育園に行くことが大事なのは、そこにちゃんとした大人がいてくれることが大きな理由です。特に家庭に恵まれていない子どもは、怖くて不安で、ギャーッと声を上げても、親に構ってもらえなかったりする。そういう子どもたちも、園に行けば怖くて不安な時にも先生たちが当然のように抱っこして慰めてくれるわけですね。この、怖れや不安などのネガティブな感情を経験した時に、信頼できる誰かと身体的に、また心理的にくっつくことで安心感を得る行動のことを「アタッチメント」と呼びますが、これをどれだけ自然に、また安定して経験できているかが、とりわけ「自分は愛してもらえる価値がある」という感覚や人に対する信頼感の発達に重要な役割を果たしていると言えます。
子どもがまさに感情の真っ只中にある時に、大人が共感してあげたり、崩れている時には元通りに立て直してあげたり、感情があまり良い方向に進んでいない時にはうまく軌道修正してあげたりすることの、一回一回積み重ねて少しずつ子どもの中で育っていくのが、非認知と呼ばれる心の力なのです。

幸いなことに、コロナ禍にあっても、今のところ保育園や幼稚園は開かれています。「保育園や幼稚園、こども園に通っているお子さんには、先生が何人かいて、家庭にも親がいる。それが、子どもにとっては理想的な状況だと思います」と遠藤先生。
遠藤:子どもたちにとって、先生や親などの大人たちは、何かあった時に駆け込める避難所であり、安心できる基地。基地の役割というのは、元気になった子どもを自分のもとに留めておかずに背中を押してあげることや、探索や冒険に夢中になれるように応援してあげること。避難所と基地の役割をバランス良く努めることが、大人の重要な務めなのです。
また、コロナ禍においてもむしろ気をつけるべきは子どもよりも親側の精神状況とのこと。
遠藤:緊急事態の中でも、子どもは楽しく健康に遊べている子が多いんです。むしろ、親の方がダメージを受けて、鬱っぽくなっている例が散見されます。ちゃんと遊べる状況があれば、子どもは楽しく逞しく成長していきますから、親は子どもに対して何か特別なことをしてあげないといけないと、と思うのではなく、親自身が明るく「変わらずにあり続ける」ことが重要。何かをしてあげないと、と思うと、子どもの先回りをしたり、後ろをついて回ったりしてしまいますが、自発的な遊びを阻害することは親子関係にとってもよくない。ただそこにいてあげればいいんです。
大事なのは、子どもが一人で何かをやっていたら、それに踏み込まないこと。夢中になれているのであれば、できるだけそれを温かく見守ってあげてください。もうひとつは、応援団としてエールを送ること。自分の力で何かをしようとしているなら、にこっとしてあげたり、声かけをしてあげたりしてあげてほしいのです。子どもは何かをしている時に、近くの大人に「見てて!」と言ってくることがありますよね。あれは「手伝って」と言っているわけではなく、文字通り「見てて」なんです。
自分自身が直接遊び相手にならなくても、黒子になってできることはたくさんあります。例えば絵本を置いておくこともそうだし、よく転ぶところがあれば家具の配置を変えてみることもそう。子どもが一人で何かをできるように下支えすることこそが大事だと思います。
完璧よりも“ほどよい関わり”を。子どもの自発的な行動が心を育てる

遠藤先生は「外に出かけて新しい刺激を受けることは、子どもにとって大きな意味を持っていると思いますし、コロナ禍でその活動に制約がかかっているのはマイナスではあります。ただ、マイナスだ、残念だと思うだけではなく、その分おうちでこういうことができたよね、ということも大事にして」と言います。
遠藤:その中で留意したいのが、大人が到底おもちゃだとは思わないようなものも、子どもは楽しい遊び道具だと考えるものだということです。そこには無限のイマジネーションがあります。子どもにとっては、棒切れ1本だって、何かを突いたり、振り回したり、何かに見立てて遊んだりするための、最高のおもちゃになるのです。わかりやすい例が段ボール。子どもは段ボールが大好きで、何かに見立てて遊んでいますよね。子どもというのは、おもちゃがなければ自分で探そうとするものなのです。そうやって自発的に何かを探して見つけたり、作ったりする経験そのものが、子どもの心の育ちに大きく働いてきます。
私たち大人の考え方は「more is more」で、多くのものを与えれば与えるほどいいと思ってしまうことが多いけれど、「less is more」ということもあります。外に遊びに行けないとか、遊具がないなどといった制約があるからこそ、子どもたち自ら何かを探したり、作ったりすることで、さらにイマジネーションが刺激され、その体験から学ぶことも多い。そういうことの大切さを、子どもの日常生活の中で捉え直す必要があると思いますね。
さらに、「子どもに求められた時には、時間がある限り、彼らの遊びに参加してあげて」とも。

遠藤:例えば、子どもたちが「ごっこ遊びに入ってほしい」と言ってくることがありますよね。荒唐無稽な遊びですが、親御さんがその遊びの中に浸かってあげることで、親子の気持ちがより近づくということがあります。特に、コロナ禍の中で在宅勤務が増えたお父さんたちには、お子さんとどっぷり関わる時間を作ってみてほしい。先進国の比較の中で言うと、日本のお父さんは子どもとの関係が特に希薄で、遊ぶ時間も最低水準なんです。当然、お母さんだけでなくお父さんも子育てをしたり、遊びに参加したりするほうが、長い目で見た時には子どもの発達にプラスに働く。これはさまざまな研究の中で、かなりはっきりとわかってきていることです。
遠藤先生は最後に、「心理学の世界では昔から言われているように、 “ほどよい関わり”が結果的に子どもの発達にはプラスに働くんです」とも教えてくれました。
遠藤:“ほどよい”というのは“完璧ではない”ということの裏返し。完璧に関わろうとしたり、現に完璧に関わったら、子どもはうまく育たないよ、ということです。どちらにせよ “あんまりちゃんと相手をしてもらえていない、気持ちが満たされない“と感じたら、子どもは黙っていないと思いますし、何らかのシグナルを発信してくると思います。そうしたら親は「あ、そうだったね」と気づいてあげればいい。完璧なんてことを考えると子育てが苦しくて仕方ないはず。むしろ、失敗の後で修復できるというのが健全な親子関係だと思います。
無理をせず、ほどよく、柔軟に。避難所と基地の役割だけは忘れずに。ちょっとした心づもりひとつで、子どもの発達、ひいては子どもの生涯にわたる“クオリティ・オブ・ライフ“にいい効果が現れるのであれば、コロナ禍でも気負わず子育てに取り組めそうですね。